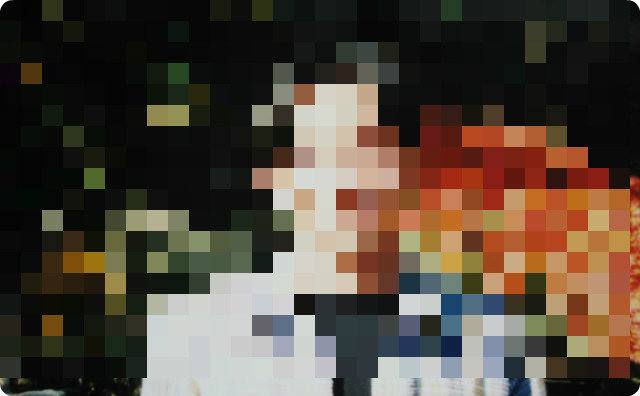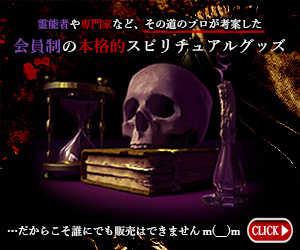【洒落怖】蛇(カガ)さまのお迎え
公開日:
:
恐怖・怪奇
参照元:http://sharekowa.biz/archives/%E3%80%90%E6%B4%92%E8%90%BD%E6%80%96%E3%80%91%E8%9B%87%EF%BC%88%E3%82%AB%E3%82%AC%EF%BC%89%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%AE%E3%81%8A%E8%BF%8E%E3%81%88.html
参照日:2018年10月16日 火曜日
関連記事
-
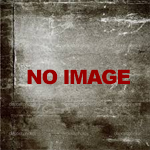
-
【洒落怖】夢で見る死体
ボクは中学生の時に、首吊り自殺死体を見た事があります。もう随分と昔の話になりますが、遺族やら何やらの
-
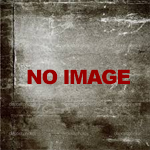
-
【洒落怖】金属の共鳴音
5年くらい前、名古屋のとある会社に勤めていたんだが、仕事の関係で1週間くらい東京に滞在することになっ
-
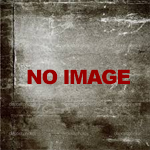
-
【洒落怖】電車で隣に座った男
電車での出来事。目つきの悪い中年男が、おもむろに持っていた新聞(因みに産経)を開いたかと思うと、新聞
-
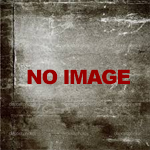
-
【洒落怖】違和感を覚えた
4歳か5歳か、小学校に上がる前の、夏の終わりの話。私は田舎にある母方の祖父母の家で昼寝をしていた。喉
-
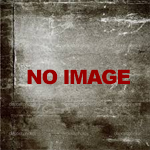
-
【洒落怖】呪いの相手
大学時代、俺にはAという親友がいた。Aは超ハイスペックで成績はいいし、外見・性格共にイケメンだった。